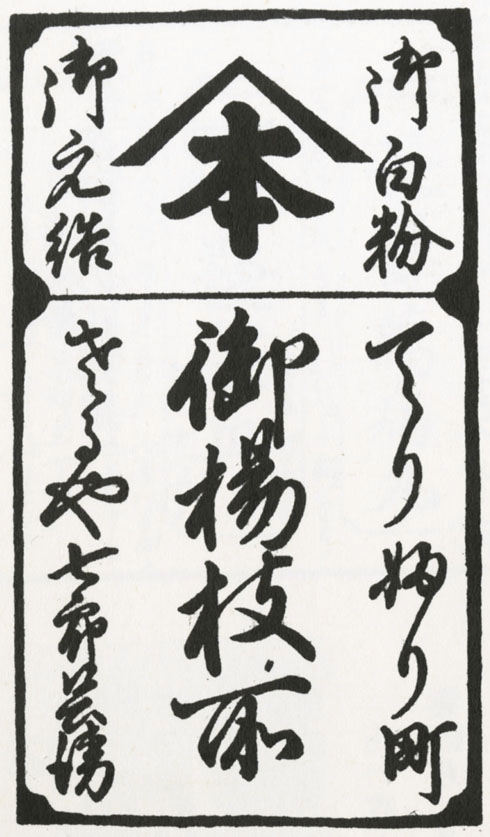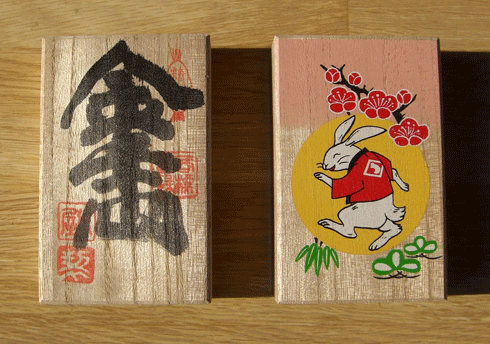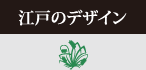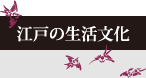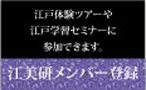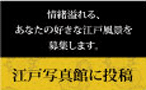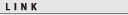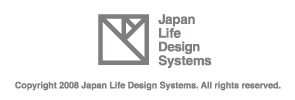暮れも押し迫った12月22日、江戸美学研究会は「浮世絵セミナー①
画狂人北斎」を開催しました。講師に浅草の木版画廊「六華庵」の島田
賢太郎氏をお迎えしました。島田氏は北斎研究をされており、2010年
「北斎誕生250年画狂人北斎」をマリア書房から出版されています。
テキストを用意して頂きました。
セミナーの様子。皆さん真剣に聞いてます。
北斎84歳の時に描かれた「田植図」の説明から始まりました。
浮世絵のヴィジュアル的な美しさだけでなく、絵の中の我々の身近な生活
につながる情報を歴史的背景を交えて説明頂きました。
「北斎の物事を見つめる心が美しい」と語る島田氏。

そして北斎誕生日を示す「大黒天図」や70年間の画号の変遷など興味
深い内容が続きました。
北斎代表作、「冨獄三十六景 神奈川沖浪裏」をご披露頂きました。
摺師長尾直太郎氏の刷った貴重な絵です。
今回はお茶と上野うさぎやの和菓子を食べながらのセミナーとなりました。
「写楽」を用いて多色刷り版画の制作工程を説明する島田氏。
摺師は1日200枚を刷るそうです。
次の日は色の調合が微妙に変わるので200枚刷るそうです。
江戸美学研究会会員の方々からの質問も鋭いものばかり。
多くの質問が寄せられ、予定より30分を超えました。
初めてのセミナーとなりましたが、小さいけれど中身が面白く、
江戸美学研究会らしいものになったと思います。
2011年は定期的にテーマを絞ったセミナーやイベントを開催します。
是非、皆様のご参加をお待ちしております。
また、師走のお忙しい中、7名の会員の方々に来て頂き感謝しております。
ありがとうございました。
それでは皆様良いお年をお迎え下さい。
□年末年始の江戸帖のお申込について
12月28日より1月4日までお休みとさせていただきます。
詳しくは下記のサイトよりご確認下さい。