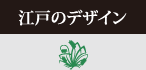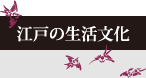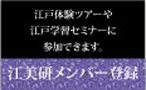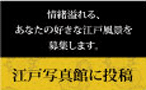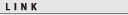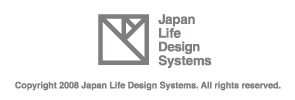江戸文字とは、江戸時代に盛んに使用された図案文字の総称で
江戸情緒豊かな、歌舞伎、相撲、寄席などに
使われる文字などを総称して「江戸文字」と呼んでいる。
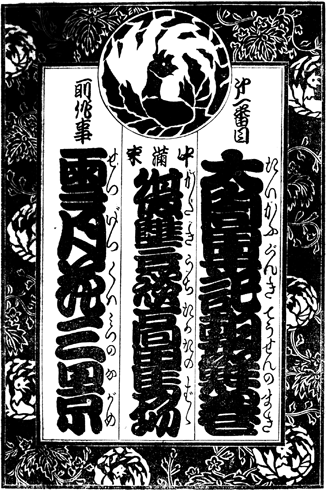

勘亭流文字は歌舞伎専用の「書」であった。
勘亭流の始まりは、徳川時代の安永8年(1779)の正月、
江戸中村座、座主九代目中村勘三郎丈が、
日本橋堺町に住む御家流書家、岡崎屋勘六に
中村座の春の狂言の大名題「御贔屓年々曽我」の表看板・番附等の揮毫を
依頼し筆を執ったのが最初といわれ、
その独特の書体は江戸市民の評判となって、
勘六の号「勘亭」から「勘亭流」の名がついたとされています。

心の雲の晴れ渡り 只一筋に向かう極楽』と、勘亭流で刻まれています。

先学の研究によれば、御家流から、浄瑠璃の床本(五行本)、狂言本を経て、
芝居文字へと至るようで、岡崎屋勘六・勘亭を芝居文字の創始者ではなく、
完成者と位置づけているそうです。
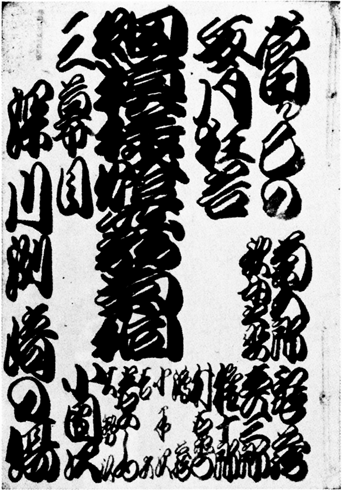

勘亭流の特徴は、
歌舞伎の舞を発想し柔らかなフォルムを表現してます。
歌舞伎界で勘亭流が使われたのは台本や楽屋表示など
宣伝物でない内向けのものと、芝居小屋の表看板や番付などで
用途に合わせて文字の大きさや読みやすさも変えるようです。
看板、番付などを書く時は、装飾的な要素が多く
「勢い」よりも「姿」に重点が置かれます。
墨をどっぷりつけ、内へ内へと文字を巻きこみながら、
枠いっぱいに隙間なく流麗に書いていきます。
勘亭流の書体には
●「字を太くすることにより隙間をなくす」(=空席が少ないように)
●「文字に丸みをもたせ尖らせない」(=興行の無事円満を祈る)
●「ハネは内側に入れる」(=お客様を芝居小屋に招き入れる)
というように、「文字」という面から、観るものを歌舞伎の世界へと
誘ってくれる意味合いもあるそうです。
また、「こんなにしても読めますか?」と、簡単に読めない程、
ぎっしりと詰めて書かれ、読めないくらいのものを読むのが
「芝居通」であるという遊び心を刺激していたようです。
文字と言う伝達機能よりもビジュアル的に
心に届くことが優先されていたのかも?
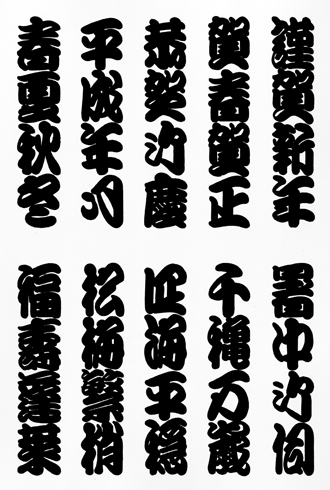
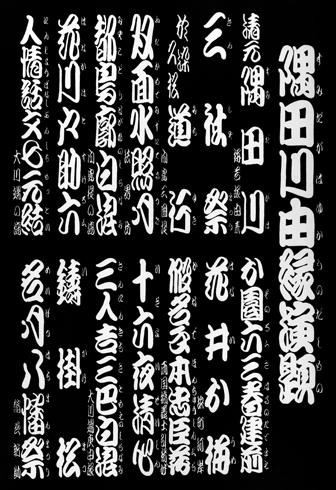
また一般書道とは異なり、姿・形を表す書法なので
重ね書きなど"補筆" をして丹念に文字を
仕上げてゆくのも勘亭流の特色でもあります。
筆は穂の短いものを使います。
特に筆の腹の部分を使うことが肝心だそうです。
墨については墨色の薄いものは不吉として嫌いますので
黒々とたっぷりとした色合いに仕上げます。
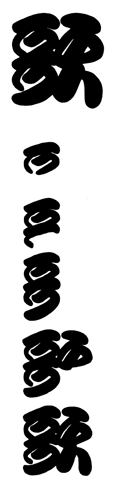
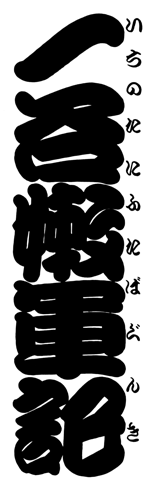
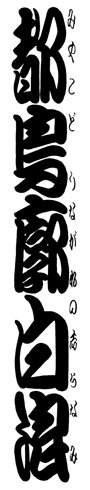
文字の書き順(上の左)はいろいろですが、
筆先をいっさい外にはねないよう内側に内側にと向かわせます。
空白部分を少なくするため、肉太に丸みを持たせ、
そして柔らかく、ゆっくりと書きます。
勘亭流はすべてがこの書き方でなく、
歌舞伎の演目により表現は異なります。
もともと人形浄瑠璃のために書かれた
歴史的な義太夫狂言ものは重々しく(上の真ん中)、
庶民生活を題材とした世話狂言もの(上の右)は軽く書くそうです。
また一般書道とは異なり、姿・形を表す書法なので重ね書き等
"補筆" をして丹念に文字を仕上げてゆくのも
勘亭流の特色と言われています-。

江戸時代(1805 年)の中村座を再現している江戸東京博物館の
常設展示の芝居小屋には勘亭流文字で書かれた看板が至る所にあります。
入口周りはとても派手で、たいへん賑わっている
当時の雰囲気が感じとることができます。
櫓には中村座の座紋「角切り銀杏」と
「中むらかん三郎 きやうげんづくし」とあります。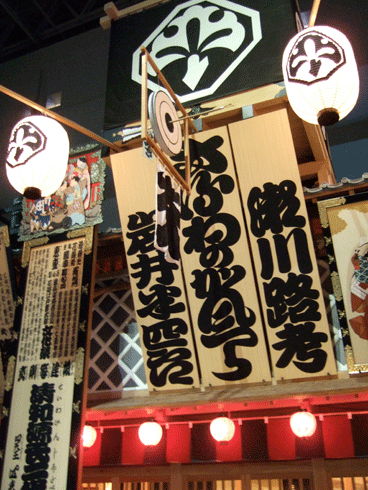
芝居小屋の正面に大きな看板が3枚あります。
右は「瀬川路考」、
左は「岩井半四郎」と書いてあるのが読めます。
真ん中がまるで読めません。
なんて書いてあるんでしょう?
係の人に聞いてみたところ
「猿わかかん三良(さるわかかんざぶろう)」と読むそうです。
いや〜難解です、崩しに崩した勘亭流文字は!
今日では、保坂光亭師(1907〜1997)が
文字と文字との間隔を毛筋一本はなした書き方に調整し
読みやすいように配慮されているようですが、
隙間が僅かな字面のイメージには変わりがありません。
江戸の庶民文化「歌舞伎」がその伝統を守りつつ
時代に応じて革新し続けているように
勘亭流文字も歌舞伎の進化に寄り添いながら
時代に沿った表現やフォルムが
少しずつ変化してきていることを感じました。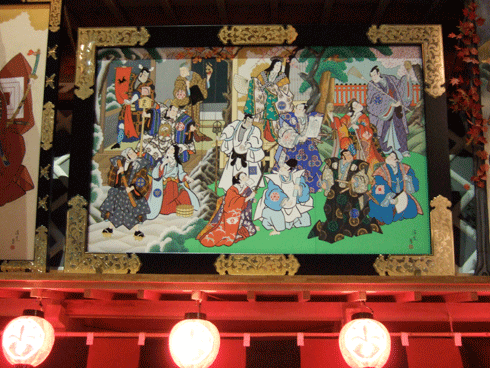
参考図書:歌舞伎座絵本番付、勘亭流字典、歌舞伎文字勘亭流読本
(松竹松山図書館蔵)