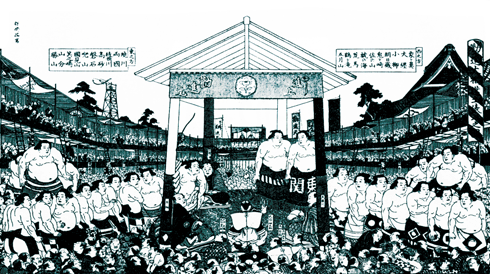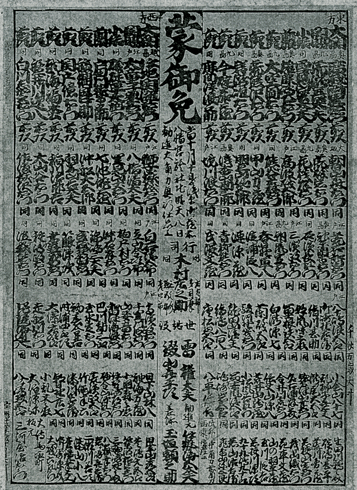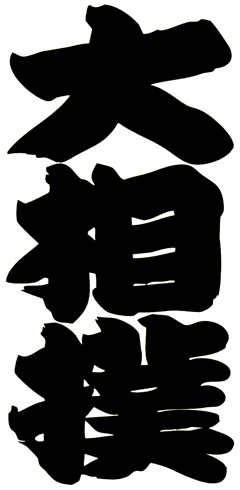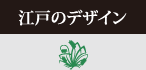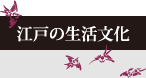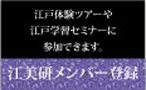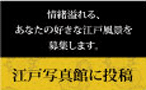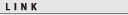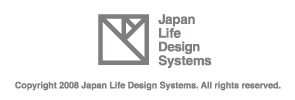江戸文字とは、江戸時代に盛んに使用された図案文字の総称で
江戸情緒豊かな、相撲、歌舞伎、寄席などに
使われる文字などを総称して「江戸文字」と呼んでいる。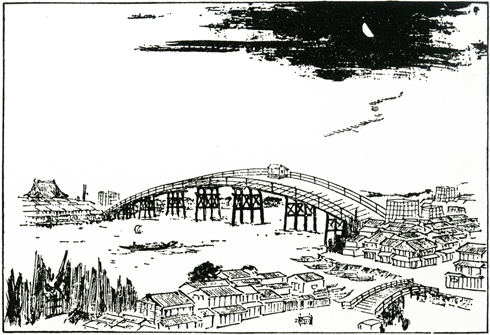
寄席、小芝居、飲食店で賑わった両国橋(宝暦時代の古図・江戸東京博物館)
両国へと見物の足を伸ばすのが、
いわば江戸見物のてはじめであったそうだ。
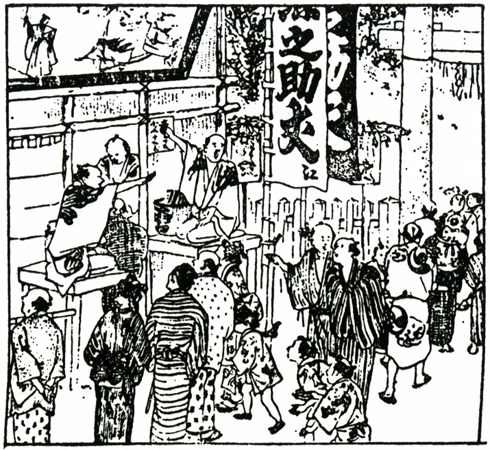
今回取上げる寄席で使われている寄席文字は、
ビラ文字がその起源である。
寛政3年(1791)、大阪から江戸に来た岡本萬作が
寄席場である議席を開き、
寛政10年(1798)、神田豊島町藁店(わらだな)に
「頓作軽口噺(とんさくかるくちばなし)」の看板を掲げ、
風呂屋や髪結床など人の集まるところにビラ、
すなわちポスターを貼って宣伝を始める。
これが寄席、そして寄席ビラの始まりで
当時の文字自体は特殊のものではなく
ごく普通のお家流だったと言われている。
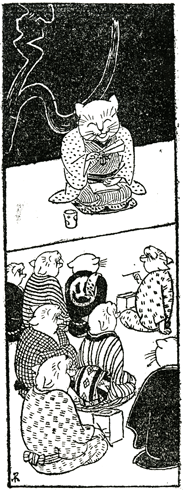
随筆寄席風俗より高座絵(江戸東京博物館)
ちなみに「寄席」という呼び名は、人を集める場所なので
「寄せ場」と呼んでいたものが「寄せ」と略され
後に「寄席」と呼ばれるように定着したそうである。
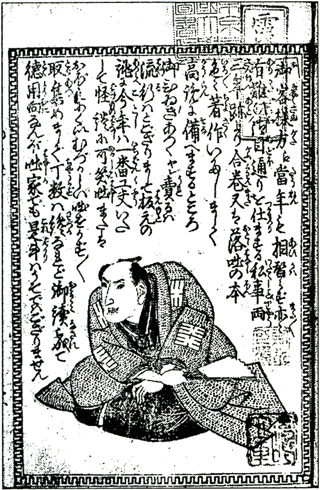
天保年間(1830〜)寄席が隆盛になったころ、
神田豊島町藁店に住む紺屋の職人栄次郎が、
本業の傍ら筆の立つことから
芝居の勘亭流と当時の広告機関であった提灯屋の文字を
折衷し、大入りを願う隙間のない
まろやかな寄席独特の文字を
創りだし書いた<ビラ>がその起こりである。

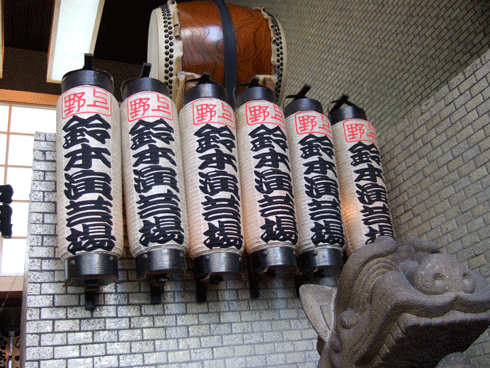
上野鈴本演芸場の提灯に書かれた寄席文字
当初はもちろん手書きであったが、
寄席の興行もますます盛んになり江戸市中には
二百軒あまりの寄席ができたという。
安政年間(1854〜)には、
需要に応じて手書きでは間に合わなく
木版手摺りの版行(はんこう)ビラが考案された。
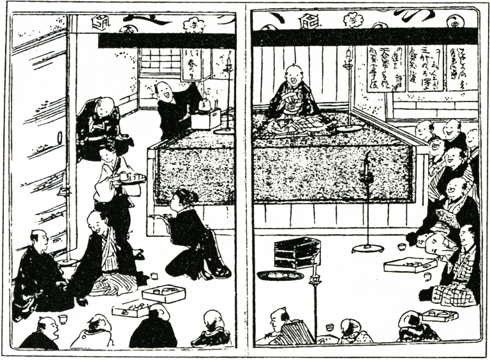
寄席文字は、墨はお客様、余白は客席の畳にたとえて
「お客様がすき間なく一杯に入ってくださるように」
との願いを込めてなるべく文字の間を空けず、
地色の白を埋めるように、
さらに客入りが尻上がりになるように
右肩上がりに書いていく縁起文字である。
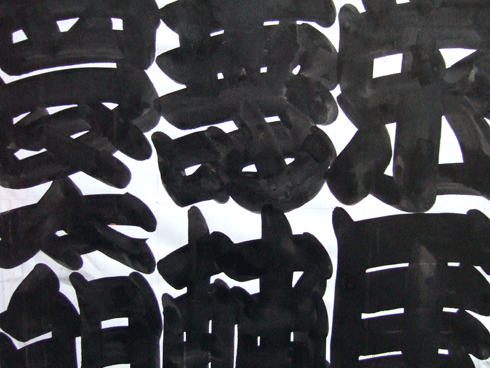
寄席文字の特徴
●余白を少なくつめて
上にも書いたように、空席を少なくという意味から、
文字間を空けず余白をなるべく少なく書きます。
●画数の多い字は書きやすい
みっちり隙間なく書くので画数の少ない字、
例えば「さん生」などの字は難しいとされている。
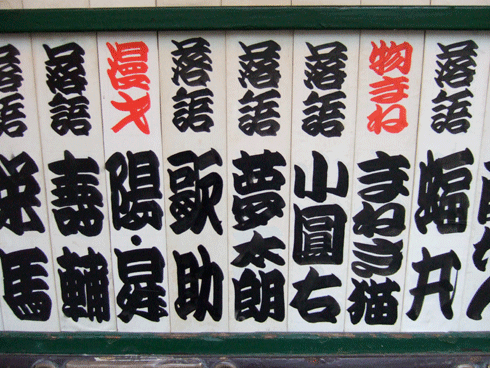
●やや縦長に書く
縦長に書くと、綺麗に見えるので、
漢字は縦:横が4:3の比率になるように。
また、ひらがな、カタカナは、正方形に書くと綺麗。
●一定の太さで線は太く
筆に墨をたっぷりとつけて、
太く、一定の太さになるように書きます。
書道のようにかすれを作らないようにするのもポイント。

●横線は右上がりに
寄席の業績や芸がだんだん良くなるようにという思いから、
横の線は右上がりに書きます。
●線は平行に
文字のバランスを考えて、
縦、横、斜めの線が二本以上並ぶときは、
平行になるように書き、
その間の余白も均等になるようにする。
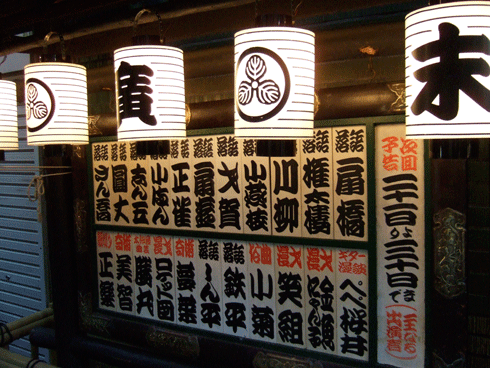

新宿末広亭に行くと迫力のある直筆の一枚看板や
四人看板、二人看板が数多く見られ
寄席独特のなんだかわくわくするような楽しい雰囲気が
館前の寄席文字から伝わってくる。
提灯に灯りがともる夕暮れ時が、寄席文字の味わいや
美しさをより一層際立たせているように感じた。