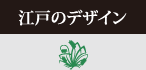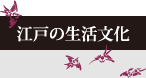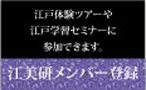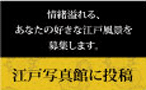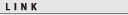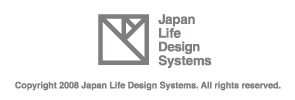この季節、植物たちはみな寒さに耐え、春の訪れを待つ。
ただでさえ花の少ないこの時期に、ひと際華やかに咲く花がある。
……それは大輪のぼたんである。
そもそも冬に咲くぼたんを寒牡丹といいうが、自然環境に左右されやすく
着花率が悪いため、厳寒でも花をつけるように栽培技術を駆使して
つくられたのが冬ぼたん。そして正月の縁起花として用いらた。
新春に華を添えるため、元旦より上野東照宮のぼたん苑では
「冬ぼたんまつり」が行われている。40種600株はなかなか壮観である。
雪がこいの中で可憐に咲く色とりどりの花をご堪能あれ。




中国原産のこの花が日本に入り、栽培されたのは8世紀頃から。
書に記されたのは枕草子がはじめ。
その後、「富貴草」「富貴花」「百花王」「花王」「花神」など、
この花の別名が示すように百花の王、高貴な花として人々に愛されたが
庶民にとっては、文字通り高嶺の花だった。
それが江戸時代に入り、栽培は盛んになり花好きな江戸の人々の目を楽しませた。
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」という言葉も
江戸時代に生まれたもの。
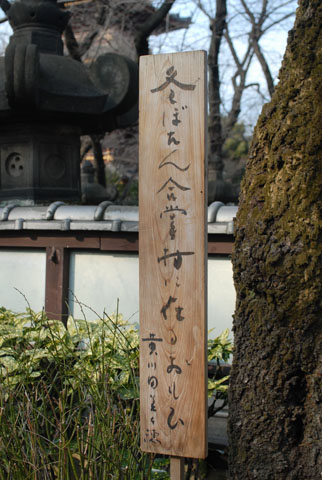




今年の上野東照宮の冬ぼたんまつりは2月20日まで開催。
春のぼたんや芍薬もいいが、冬の景色に凛として咲くぼたんもまた格別。
火鉢にあたり、甘酒を飲みながら苑内をまわれば、
ヒマラヤサクラなども咲き、春の足音を感じさせてくれる。
江戸美学研究会で一緒に江戸を楽しみ、
一緒に研究してくださる方の
メンバー登録もお待ちしております。
⇒ https://www.jlds.co.jp/ebilab/moushikomi.html
ご好評いただいております『江戸帖 EDO DESIGN DIARY』、
書店等のお取り扱いがそろそろ終了いたします。
購入ご希望の方はコチラからご注文ください。
⇒ http://www.jlds.co.jp/edotyo/