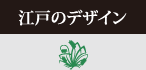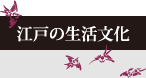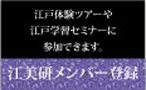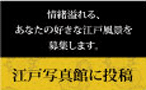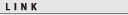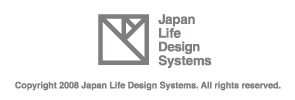「いくよ餅」は、焼いた餅に餡をまぶした、
あんころ餅のようなもので
江戸時代中期、両国の名物餅であったといいます。
「いくよ餅」の説はいろいろありますが
元祖は元禄17年に創業した
西両国の小松屋であるといわれています。
車力頭の小松屋喜兵衛が
新吉原河岸見世の遊女・幾世太夫を妻に迎え、
両国橋の西詰めで幾世自らが焼いた
あん入りの餅を「いくよ餅」と名づけ
売り出したのが始まりのようです。
1個5文で売り出したところ、町中で大人気となり
偽物まで出る始末となったそうです。
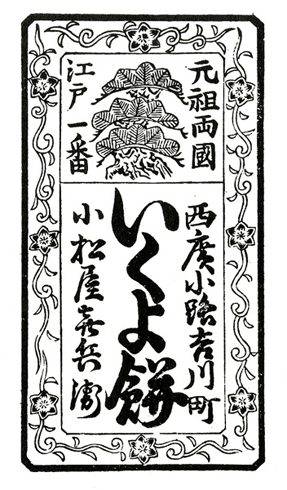
この商標は、その小松屋のもので上部中央には
神迎えの標木として重要な意味をもつ松をデザインした
家紋的な「変わり荒枝付き三階松」が
シンボルとしてに配置されています。
松は常緑で不老長寿に繋がるとして平安時代から
吉祥の象徴とされてきたことから
永々と店が続いていく意味も持たせていたと推測できます。
その下には真ん中に江戸文字で「いくよ餅」と書かれ、
商品の存在感を力強く表現しています。
左右には、地名の「西広小路吉川町」と
主人名の「小松屋喜兵衛」の文字が配され、
情報としても的確なものになっています。
周りには草花の飾り罫をほどこすデザインから
全体的に重厚感や華やかさを出すようにしています。
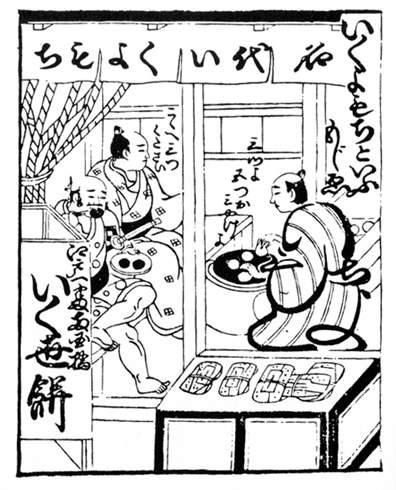
——入口に掛けたる太き縄すだれ、ねじりてちぎり出す幾世餅——
——見付けから くひたさうなる 幾世餅——
などの狂歌が当時のままを描いていることがわかります。
他にも「いくよ餅」には、自分の方が元祖という店があったそうです。それは、浅草御門内の藤屋という店です。
餡餅の創業はこの浅草御門内の藤屋市兵衛の方が
早かったという説もあります。
小松屋が「幾代餅」で繁盛したので、
藤屋は元祖であることを主張して
大岡越前守に訴えを起こしたといいます。
結果は、藤屋は葛飾新宿。
小松屋は内藤新宿に移って商売をするようにとの裁きとなったそうです。
もうひとつは、両国吉川町の若松屋といわれていますが、
小松屋が後に若松屋となったともいわれ、これも定かではありません。
江戸中期に大変繁盛し、明治以前には姿を消した「いくよ餅」。
江戸っ子たちが愛したその味を楽しみ、
その意匠を目にすることができないのは、とても残念なことです。