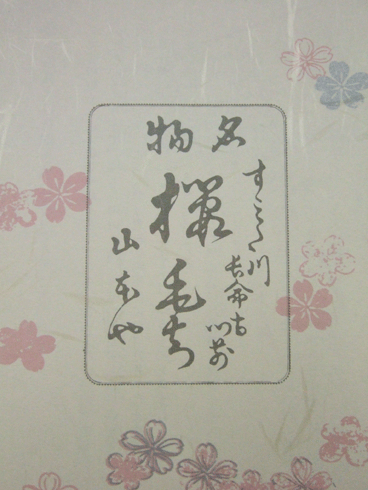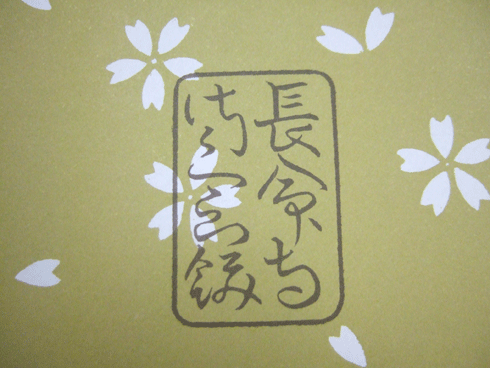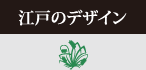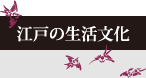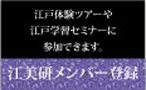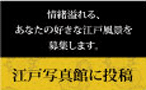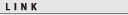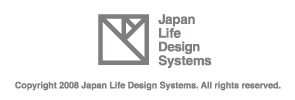「桜もち 食うて抜けけり 長明寺」
「三つ食えば 葉三片や 桜餅」
俳人・高浜虚子も此処を訪れ、詠った「桜もち」について調べてみました。
江戸向島の長命寺門前には、何軒かの桜もちを売る店があったそうです。
その内でこの商標の店「山本屋」が桜もちの元祖と言われています。
創業は徳川八代将軍・吉宗の享保二年(1717年)になり
現在まで約300年余り続く老舗店です。
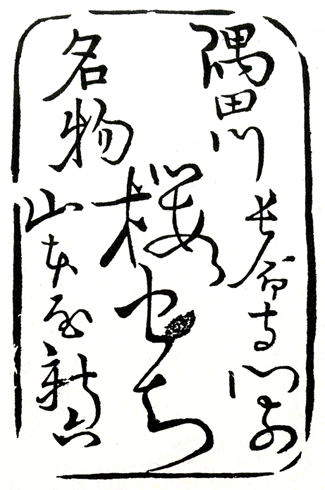
長命寺は、元須崎三丁目にあって常泉寺と言われていましたが
寛永年間(1674年)徳川三代将軍・家光が鷹狩りの帰途、
気分が悪くなり、この寺に休んだ時に、
住持の孝海が境内の井戸の水をさしあげたところ
気分が爽快になったそうです。
喜んだ家光が、この水を「長命水」と名付けたので、
以来この寺も長命寺と呼ぶようになったそうです。
江戸中期、この長命寺がある向島堤には数百本の桜の苗が植えられ、
桜の名所となり多くの人が訪れたそうです。
長命寺の門番をしていた銚子に先祖をもつ山本新八という人が、
おびただしい桜の落ち葉を掃除しながら、
それを無駄にするのが惜しくなり、
試みに桜の葉を醤油樽に漬けて売ったそうです。
その後こんどは、小麦粉を溶き、薄い鉄板の上でのばして白焼きとし、
中にあずきの漉し餡を包み二つ折りにし、
さらにその上から塩漬けの桜の葉で包み、
これを桜もちとして売ってみたところ、
立ったまま手軽に食べられるので大人気となったそうです。
これが「桜もち」の始まりだと言われています。
この桜もちは、中の餅が薄い小麦粉皮であることと、
桜の葉が両面から一枚ずつ包んであり、
葉の香りがほのかに移るのが大きな特徴でした。
淡味津々情趣あふれるこの餅の風味が江戸人の好みにぴったりと合って、
桜もちの名は一世を風靡したようです。
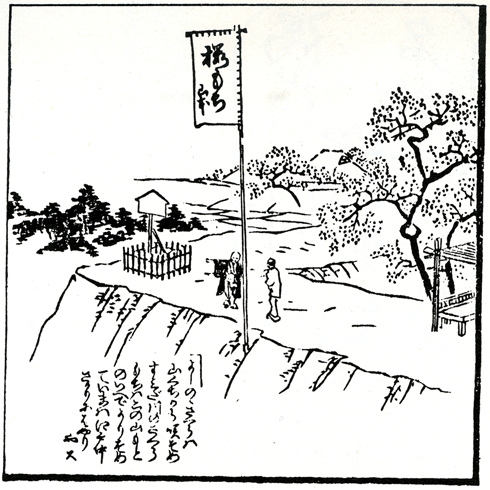
上の「面白草紙噺図会」(天保十五年)の詞書には、
「よしのさくらは山ぐちから咲きそめ、
すみだ川のさくらもちは、この山もとのいへでうりそめて、
いま江戸中さかりにはやります」とあります。
翩翻と川風に翻る幟は「江戸名物詩初編」に
「幟りハ高シ長明寺辺ノ家」と詠まれていて、写実の風景であり
幟には「桜もちと山本」の字が描かれています。
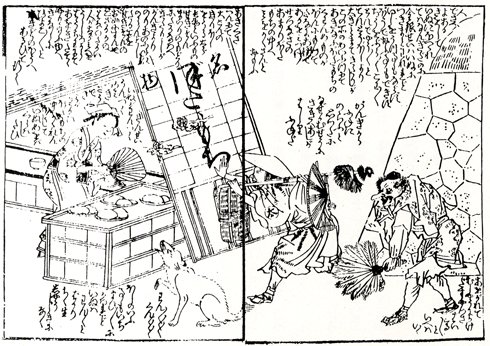
下の写真は現在「山本や」で使用されている
パッケージに貼られる商標上紙と包装箱です。
どちらもそれぞれ時代と共に少しずつ表情を変えてきていますが
いまも江戸の風情を感じさせてくれています。