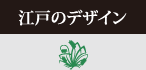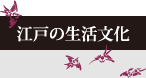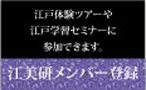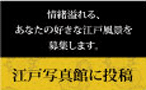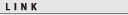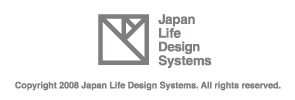昨年6月にスタートした江戸の商標ブログは
「笹乃雪」、「山本山」、「永代団子」、「にんべん」、「酒悦」、
そして「さるや」の6回でした。
今年の商標ブログを始める前に、
そもそも江戸時代の商標の始まりは?を調べてみました。
(本来は、最初にやるべきものなんですが………)
江戸時代の商標の始まり
江戸に幕府を設けた徳川は、
大名の力を弱めるために参勤交代の制をとりました。
そのため、三百有余の大名及びその家臣、
家族も江戸生活を余儀なくされたので、
生産業の未だ発達しない江戸に人口が集中し、
江戸は物資の大マーケットとなりました。
元禄の頃には、とても太平となり生活がより向上し贅沢となったので、
商品の需要は急激に増加していったようです。
商品の流通は江戸を目指して商品が送られるのが自然ですが、
江戸に向けて大量の物資を輸送するに便利な海運は、
まだ発達していませんでした。
そこで大阪を結ぶ航路がたいへん重要となっていました。
特に大阪は周辺に物資の生産地を控え、
大量の商品が集中する地であったため、
重要物資は一旦大阪に集り、次いで江戸に向けて輸送していました。
米、味噌、炭、酒、醤油、油、木綿、綿などの大きな荷は、
ひとつの大船に混載されることから、
他の同業者の同一商品の積荷と混同することが多かったようです。
そうした混同を免れるために、
荷に業者の荷印をつけるようになりました。
荷印には生産者、もしくは販売者によって自分の製品を
他の製品と区別するためと、製品の優れていることを
他の人に認めてもらう媒体とするために
独自のネーミングや文字デザイン、そして意味のある図案を
荷印に表現する必要があったと思われます。
これが、江戸時代に商標が始まった元と言われています。
荷印のついた積荷は各港に陸揚した後も、
この業者の荷印がついたまま町中で売買するようになり
ついに荷印が商標として、その存在価値を高め
製品や店を識別する銘柄となっていったのです。