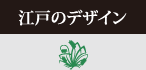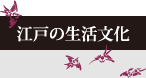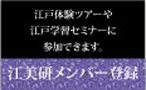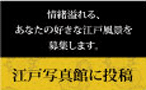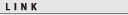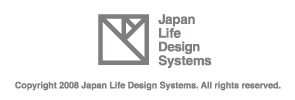時代劇に登場する江戸の大店の看板は、大きな板に文字を彫り漆や箔で加工
した立派なものだが、未だその手彫りの技を継承する額匠は東京に3軒。
その一軒である坂井保之さん、智雄さん親子は合羽橋本通りに店を構える。

「看板の基となるものは、仏教の伝来とともに日本に入ってきました。
寺社の門殿などに名称を書いて掲げたものを扁額といい、これが後に
江戸の町民文化の成熟と共に看板に応用されるようになりました」。
智雄さんが話すように看板が文字看板、行灯看板、幟看板、模型看板、
判じ物看板など、様々な形で発展したのは江戸時代。
それは、華美なものへとエスカレートしていったという。
江戸の初期頃までは文字を読める人も少なく、売り物や商売の内容を
絵で表現していたが、江戸文字や寺子屋文化の発展により、
町人も字が読めるようになると共に、
八代将軍、吉宗の質素倹約の幕政を反映して
文字看板が主流になったのだそう。

漆と金箔で仕上げた看板が軒先に掛けられている。
実際につくられた看板を見ると、文字は立体的に浮き出して見え、
遠目にも文字の存在感が増す。
これをかまぼこ彫り、額彫りと呼ぶ。
これらを彫るのは、「看板刀」と呼ばれる切り出し1本のみ。
大看板から携帯ストラップのような小さなものも
楷書、草書、篆書、隷書、江戸文字など書体も色々、
すべて看板刀で仕上げる。
彫る、漆を塗る、箔をはる、みんな手仕事である。


看板刀は刃の中央が山形になっているのが特徴。柄の部分は手に合わせて手作り。

看板刀を逆手に持ち、板に立て込んで手前に引く。


小さなものでも文字の彫りの美しさ、漆の仕上がりは大きなものと変わらない。
坂井さんが手がけた仕事は、
日本橋三越の印の修復、花園饅頭、塩瀬総本家など老舗の看板があるが
それだけではない。
名だたる寺社の扁額、千社額、招き札、表札なども多く手がける。
「うちの仕事は、オールラウンド。寺社仏閣からその筋の人まで」
と保之さんは笑う。

江戸家子猫さんの猫八襲名披露のための招き札。

北京五輪バタフライ銅メダリスト松田丈志の記念招き札。メダルの部分にはブロンズ箔がはられる。

扁額や看板というと、普通の人には縁のないもののように思うが
存外、今人気があるのが招き札だという。
「京都 南座の顔見世の招きあげを見てもらえるわかりますが、
上方の招き札は木に勘亭流の文字を書いただけのもの。
江戸では、文字の輪郭を彫り、
塗りで仕上げるという違いがあります。
長い間、そうした江戸から続く芸能の世界や
祭の会などでやりとりされていた招き札ですが、
襲名披露などで目にすることも多く、かっこいい!
と思われる人も多いようですね」と智雄さん。
縁起物として何かの記念につくる人も多く、
出産の祝いに名前と出生時の記録としての注文もあるのだそう。
「私たちの仕事のいいところは、仕事が残ること。
看板も扁額も千社額も招き札も表札もみんな木とともに歴史を刻んでいく。
看板の「看」の字は目の上に手と書く。
これは、目の上に手をかざして上を仰ぎ見るという意味。
そんな有り難い仕事はないね」と保之さんは続ける。

(右から)台東区無形文化財の福善堂 三代目の坂井保之さんと
嫁いでから下ごしらえ、仕上げの仕事を覚えたという
奥さんの節子さん。大学を卒業後すぐに修行をし、
4代目となる智雄さん。
木と漆の香りのする仕事場で愛犬とともに記念撮影。
お仕事中、取材にご協力いただき、ありがとうございました。
福善堂 坂井看板店 http://www.interq.or.jp/tokyo/fukuzen/