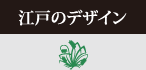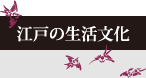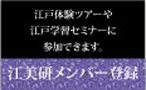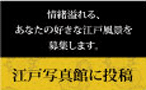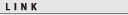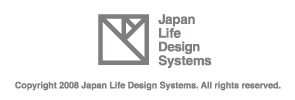——願わくば 花の下にて 春死なん その如月の 望月のころ——
これは、平安から鎌倉にかけて武士として僧として歌人として
生きた西行の辞世の句である。
花見の起源は奈良時代に貴族の間で行われた行事であったという。
当時の花は梅であったが、平安の頃になると桜となり、
「花見=桜」は現代まで続く。
この句に詠まれている花もまた例にもれなく桜である。
広く花見の風習が庶民にまで広まったのは江戸時代のこと。
八代将軍吉宗が江戸の各地に桜を植えさせ、花見を奨励したからだ。
——花の雲 鐘は上野か浅草か——
曇り空に咲き誇る桜と鐘の音を重ね合わせた芭蕉の句。
芭蕉はこの句を深川の庵で詠んだといわれる。
将軍家の菩提寺であった寛永寺の桜は、それは見事なものであったが、
歌や踊りを禁じられていたため、もっぱら庶民は隅田川堤や
王子の飛鳥山、御殿山、小金井堤まで足を延ばして
酒を飲み、歌い踊り、遊山を楽しんだという。
これが一年のうちでとっておきの楽しみだったことは
正月に着物を新調するのを我慢してでも花見のために誂えて出掛けた、
という当時の女性の心境からもわかろうというものだ。
今年は、灌仏会の日(4月8日)の下町の桜をご紹介。
ところは、上野と浅草の間の元浅草から松が谷にかけて。
ここいらは江戸から小さな寺院がひしめくあたりだ。
名所までいかずとも寺の庭も狭い家の敷地にも、
敷地をはみ出した鉢植えにもさまざまな種類の桜が
春の陽射しをうけ、咲きそろう。
しばし、花見をご堪能あれ。

江戸にはもうひとつ桜の名所があった。
浮世絵にも多く描かれた吉原の夜桜……。
女たちには縁のない郭もこの時ばかりは町家の女達も訪れたという。
もともと、吉原に桜はなかったが、この季節にだけ染井の植木職が
仲の町の大通りに移植した。その数100本といわれる。
そしてつかの間の花が終わるとまた元の景色に戻したというから
その技術と江戸の美意識は底知れぬ。
まさに「諦め」と「潔さ」の美学である。
そろそろ花散らしの雨がくるころ。
また次の春までのお楽しみというところで……。
——散る桜 残る桜も 散る桜—— 良寛