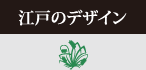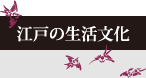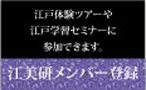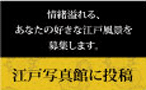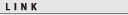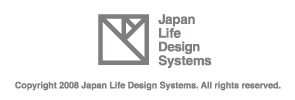11月26日は、いよいよ三の酉。
日付がかわる頃には、今年一年の感謝、
そして新年の幸運を願って多くの人がお酉さまに駆けつける。
江戸の遊び心と洒落が盛り込まれ、徐々に華やかなものになった熊手だが、
もともとは近郊の農家の副業だったと語るのは
長年、浅草鷲神社に店を出す「八百敏」の清田一彦氏。
上の写真の立派な熊手も清田氏の手によるもの。
注連縄や俵、お多福もみな手作りだ。
一年かけて作った熊手が日の目を見るのは酉の市だけ。
寒風のなか、準備に三日間泊まり込むという。
三の酉まである年は大変だ。



PHOTO:KATSUMI YOSHIDA
さて、熊手の買い方をご存知だろうか。
最初から大きなものを買うのではなく、年々大きなものに買い替えていく。
福に感謝し、育てていくのだ。
そして値切ってまけてもらった分はご祝儀として店に渡す。
これも福を独り占めしない江戸っ子の「粋」。
必ずそうしなければならないという慣らいではないが、
みんなが幸せに、気持ちよく年を越したいというのが江戸っ子の美意識なのだ。
最後に三の酉の年に火事が多いと伝えられるのは、
お酉さまを口実に吉原に通う亭主を足止めするために
女房たちが言い出したものという説が有力ともいわれる。
ひと月に三回も吉原通いをされたんじゃ、そりゃぁ、たまったものじゃない。
「お前さん、三の酉までの年は火事が多いっていうじゃぁないか。
外をふらついてて火事にでもなったらどうするんだい」
なんていう会話が、すぐそこから聞こえてきそうだ。………お多福に熊手の客がひっかかり………
※江戸美学研究会編集2012年版『江戸帖』でも八百敏のご紹介をしています。
http://www.jlds.co.jp/edotyo/2011/07/post-3.html