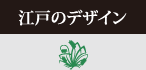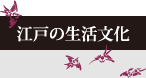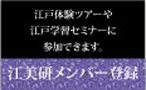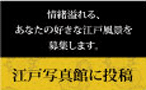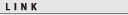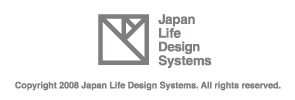節分あけましておめでとうございます。
いよいよ平成23年度が本格的にはじまりました。
「節分」は季節をわけるという意味で、立春、立夏、立秋、立冬の前日を指しておりました。
江戸時代以降、立春の前日を「節分」と呼ぶようになったようです。
今回、三大稲荷の一つ、笠間稲荷神社東京別社(中央区日本橋浜町)の節分追儺式(ついなしき)に行って参りました。
笠間稲荷神社の本社はあの笠間焼きで有名な茨城県笠間市です。
それがなぜ中央区に?と思われる方も多いと思います。
日本橋浜町かつて笠間城主、牧野家の下屋敷がありました。
江戸末期笠間藩主の牧野貞直公が本社より御分霊を奉斎し、建てられたのがこの東京別社です。
神事が終わり、いよいよ豆まきがはじまります。
季節の変わり目は邪気(鬼)が生じると考えられており、
鬼に豆をぶつけることで邪気をはらったわけです。
現代では豆だけではなくお菓子もまきます。
(昔は五円玉の束もまいてました。)
皆袋をもって待ち構えてます。

「鬼は~外~!福は~内~!」
少々わかりづらいですが、ピンク色のお菓子が宙を舞ってます。
まく側からの眺めです。
今回54年連続で参加されてる方がいました。
もちろん参加回数最多の参加者です。
祭りのあと。
豆やお菓子の残骸が残ります。
今回まいた豆です。
自分の数え年と同じ数の豆を食べます。
また、自分の年の数の一つ多く食べると身体が丈夫になり病気にならない
と言われてます。
ところで皆さんもお家や神社で豆まきをしましたか?
皆さんの新たな一年のご健康を祈願します。