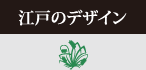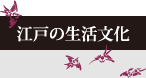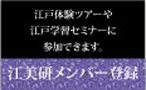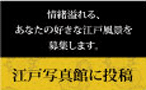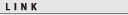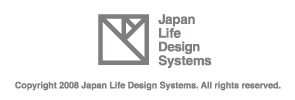今年1月、江戸美学研究会に山形県の酒田市立第三中学校の先生より
修学旅行のご相談をいただいた。
東京への修学旅行中、江戸の風俗──特にファッションについての
グループ研究をしたい生徒さん達がいるが、訪ねてよいかとのこと。
思いがけないお問い合わせであった。
しかし「困ってる人は放っとけない」のが江戸の人情、江戸の美学!
ということで、実際に資料を見せていただけて、
お話を伺える取材先をアテンドさせていただくことと相成った。
今回は、修学旅行当日の様子をレポート!
4月22日(木)
朝からあいにくの雨模様。宿泊先に迎えにいくと待っていたのは女の子4人。
まずは、江戸時代の女性の髪型や化粧についてのお話をうかがうために
最寄りのポーラ文化研究所のポーラ化粧文化情報センターを訪ねる。
なぜ髪を結っていたのか、流行の髪型、どうやって手入れをしていたのか、
どのくらい髪は長かったのか、化粧の仕方、化粧道具などなど……
お話を伺いながら、資料を拝見!
お歯黒のための鉄血(かね)を再現したものも見せていただいた。
とても口に入れるものとは思えない臭いにビックリ。

一生懸命ノートに書き留める。果たして漢字は分かっているのか!? ハタと思う。
場所を合羽橋に移して、取り敢えずランチ。
移動がてら合羽橋といえば……ということで食品サンプル屋さんに立ち寄る。


合羽橋の「ワッフル Y」でランチ。メニューはムール貝ときのこのショートパスタ。
訪ねた先は浮世絵版画と和小物を扱う下町木版画廊。
浮世絵の刷り方や絵から読み取るその時代背景、ストーリー、江戸の洒落
など、美人画を見ながらお話いただいた。
浮世絵には、江戸時代の風俗を読み解くヒントが隠されていて実は奥が深い。

もう少し大人になったらこの美しさを理解できる日が……。
最後に日本橋の三越前で銀座線下車。
三越の大きさとその風格に一同、驚きを隠さない。
向かう先は小舟町、この辺りは
今、TBSドラマ「新参者」の舞台、人形町にほど近い。
1842年創業の老舗、竺仙で当時の流行や現代の着物との違い、
どのくらいの値段だったのか、
ひとりどれくらいの着物を持っていたのかなどを伺い、
小紋の着尺と型紙なども見せていただいた。

小紋柄の型紙。今は数少ない職人による精緻な手仕事に見入る。
10時から15時までの短い時間の江戸の修学旅行。
この日は徐々に雨あしも強くなり、4月も半ば過ぎとは思えない寒さ。
慣れない街を歩き、混み合う電車に乗り、彼女たちはさぞ疲れたことと思う。
そして、少し難しいところもあったかもしれない。
でも少しでも江戸文化に触れ、記憶にとどめ、
江戸美学のよき理解者になってもらえれば嬉しい限り。




小澤 翠さん、佐藤愛美さん、草深夏美さん、小池杏奈さん、お疲れさまでした。
また、今回ご協力くださいました
ポーラ文化研究所 富沢洋子さま、下町木版画廊の島田賢太郎さま、
竺仙五代目当主 小川文男さま、ありがとうございました。
【ご協力先】