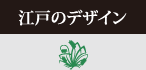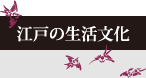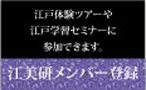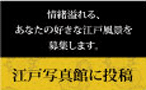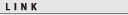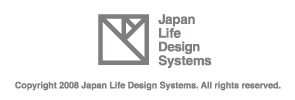宮出しが無かった昨年とは違い、早朝6時から宮出しを撮ろうとする報道ヘリが上空を飛 ぶ。桜が終わる頃から〝気分は祭り〟とにかく浅草に足が向く。三社祭は、昼近くになれば、各町内のさまざまなデザインの神輿と本社神輿が通りの両側を連ね る様がなかなか見応えがある雷門通りは鈴なりの人だ。どんだけ他所から人が来ようと氏子にとっちゃぁ、祭は神事である。神輿は熱気と圧迫感、一体感が入り 交じる昂揚、それでいて粛々と進んでいく空気がたまらない。江戸時代には、神輿は浅草御門から船で隅田川を遡り、花川戸辺りで陸にあがって練歩いたってぇいうから、今よりももっと派手な祭だったに違いない。ちょいと、観てみたい気がする。

三社祭は3日間とも晴天に恵まれることは珍しい。今年もご多分に漏れず雨、それも朝はどしゃ降り。写真は、かっぱ橋での三之宮。担ぎ方は神田祭、鳥越祭と同様、もちろん江戸前担ぎである。「せいや、さー」「そいや。そいな」など担ぎ声に合わせて腰でリズムをとるように神輿を揉む(因に深川明神や冨岡八幡寓の担ぎ声は「わっしょい」)。これが、存外難しい。

─やせ我慢 粋と痛さを天秤にかけりゃぁ 粋が重たい 江戸神輿─

祭半纏コレクション
半纏は、渋好みの江戸っ子らしい色使い。無地もあれば江戸柄の「くぎぬき繋ぎ」「吉原繋ぎ」「網目」などさまざま。半纏の下のだぼシャツの柄も"粋"を競うように洒落る。普段どんなにセンスがよくても、祭り装束が野暮ったかったら興醒めなのだ。
半纏は、渋好みの江戸っ子らしい色使い。無地もあれば江戸柄の「くぎぬき繋ぎ」「吉原繋ぎ」「網目」などさまざま。半纏の下のだぼシャツの柄も"粋"を競うように洒落る。普段どんなにセンスがよくても、祭り装束が野暮ったかったら興醒めなのだ。


コラム
THE ASAKUSA
では、ちょっとファッションチェック。縞の太さといい帯の大胆な柄といい、なかなか着こなせないコーディネート。これは神田あたりじゃお目にかかれない。注目は足元。下駄でも草履でもない、雪駄である。早足で裾さばきも颯爽と歩く姿は、手練たものだ。