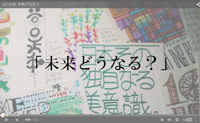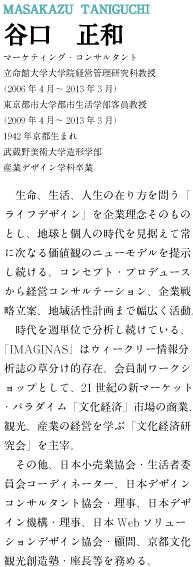 
|
2016年11月29日 田原桂一 光画展
パリは自らの中にある未来への可能性を孵化させるインキュベーションシティ。
京都も古い根があるがゆえに同じ特徴を持っている。
このダブル感性を持っているのが、京都生まれでパリに渡った写真家の田原桂一さん。
画像
光と影の中側に、鋭い抽象性を映し出すモノクロームのカメラマン。
現代にデジタルで蘇った水墨画を見ているような心地である。
生きて暮らすことが感性のすみか。そこをすくい上げる視覚詩に囲まれた感動を報告する。
京都 何必館で12月25日まで展示開催中。
パリは自らの中にある未来への可能性を孵化させるインキュベーションシティ。 京都も古い根があるがゆえに同じ特徴を持っている。 このダブル感性を持っているのが、京都生まれでパリに渡った写真家の田原桂一さん。

光と影の中側に、鋭い抽象性を映し出すモノクロームのカメラマン。 現代にデジタルで蘇った水墨画を見ているような心地である。 生きて暮らすことが感性のすみか。そこをすくい上げる視覚詩に囲まれた感動を報告する。
京都 何必館で12月25日まで展示開催中。
2016年11月22日 日本企業 CEOの覚悟日清HDのCEO安藤宏基氏が3冊目の書籍『日本企業 CEOの覚悟』(中央公論新社 税別1500円)を上梓された。 
2代目として、経営にただ新しいものを入れるのではなく、何を引き継ぎ何を成長させるのかという認識のプレゼンテーションノートである。 オーナー経営の中で創業一族が大きなリーディングを持っているところは、速度が特徴であり合理性を超えた時代への直感力がある。 個別の利益を語る経営から、課題解決と社会評価を軸足にする経営へ。日清食品はカップヌードルを世界食品にするというにらみにおいて、カジュアルなインスタント食品を文化とリンクさせインフラフードとして成熟させた。 世界的にひとつの領域を担おうという課題を引き受け、カップヌードルミュージアムというソーシャルプレゼンテーションを観光をベースとしても組み立てている。 2020年に向けて1兆円のグローバルカンパニーとして価値創造を引き受けた覚悟が綴られた本書に、社会経営のヒントが多く眠っている。 2016年11月15日 武士の家訓この本は創元選書から1944年に刊行された書籍を講談社学術文庫が再発行したものだ。

1944年は私の父は32歳、創元社で創元選書の編集者として働いていた時期だ。 著者である桑田忠親氏は、私の東急時代の上司である桑田瑞松さんの父であり、我々の知らない世界でそのようなつながりがあった奇遇に感謝し、驚きを込めてこの本をいただいたのでここにご紹介する。 セオリーやメソッドと言われるような企業の心得もまた武家の家訓と同じような性格を持っている。特に今は混沌とした戦国の世であり、いかにして生き延びるかという英知の伝承が再び重要性を増している。家訓とは体験が英知にまで至ったソフト財。そういう意味では、体験をセオリーに変え、伝承すべき心得として繋いでいく時期が来ている。正に求められた再出版である。 2016年11月 8日 食の金メダルを目指して三國清三さんは北海道増毛から上京し、18歳から2年間東京の帝国ホテルで働き、それが認められて駐スイス日本大使館料理長に任命された。 30歳で帰国し四ツ谷にオテル・ドゥ・ミクニをオープンさせ、食文化や食そのものを人生とイコールにしてきた。 この度、フランス レジオン・ドヌール勲章シュバリエの受賞パーティにご招待いただいたので私も駆けつけた。 プレゼントいただいた『食の金メダルを目指して(日本経済新聞社 税別850円)』は2020年に向けて食への未来構想を描いたおもてなしブックであり、彼の魅力がよく記されている。

子供の食育や江戸野菜の復活に取り組み、日仏を超えて食文化の架け橋を引き受けてきた魅力的な生き方にエールを送る。 2016年11月 1日 『葬式に迷う日本人』私の友人の一条真也さんが、葬式は不要と主張する宗教学者の島田裕巳さんと往復書簡という形で論議し、それを1冊の書籍としてまとめた『葬式に迷う日本人』(三五館 税別1200円)。

生き方と死に方を分けて考えずに、死生観を従来の葬儀を超えて次なる生き方を表現していくという意味合いで、死者の魂と遺族の心にどういう認識を提示できるかということが論点。 当面葬儀は消えていく流れの中で生まれ直していくだろう。 生きることへのサヨナラの告げ方を改めて考える時代である。 |