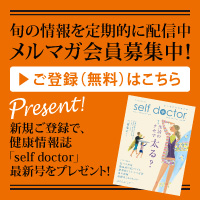ノルディック・ウォークで無理なく体力づくり

松本陽子健康体操研究所代表
松本陽子先生
1979年に愛媛県で健康体操研究所を開いて以降、健康運動指導士としてさまざまな取り組みを行ってきました。
健康運動指導士とは、スポーツクラブなどで直接体育指導を行う運動の専門家なのですが、理学療法士や保健師に比べて認知度は低く、当初は四国でも私のみという状況でした。
でも健康長寿社会が到来するこれからは、現場型の健康運動指導士の必要性はもっと高まっていくと思います。

●高齢者にすすめたいノルディック・ウォークとは
先般、高齢者研究をしているある先生から、高齢者は運動をすると認知障害を防ぐことができる、とお聞きしました。
多くの高齢者は足腰が弱っていますから、筋トレとストレッチをしっかり行うように指導していますが、そうすると身体の痛みも和らぎ自然と歩けるようになります。
どんな高齢者でも椅子に座りっぱなしや寝たきりにならず、まずは立ち上がって歩くことが大切。
それが認知症防止にもつながるのであれば、なおよしですね。
とはいえ、例えば一度痛めた骨に長時間負荷をかけるようなことは避けなくてはなりません。
そこで2本のポールを使って歩行する「ノルディック・ウォーク」に注目しまして、09年に「えひめノルディック・ウォーク協会」を立ち上げました。
もともとスキー選手の夏場のトレーニングとして実施されていたのですが、それに医学的な裏付けを付けたフィンランドから世界へと広がってきたのです。
日本でも17年位前に宮下充正先生によって伝えられ瞬く間に拡大、今では全国大会も各地で開催されています。
ノルディック・ウォークは、アスリートのトレーニングから高齢者の体力づくり・障害者のリハビリ・「歩育」として幼児から子供達にまで広がってきています。
高齢者が大会に臨む時にいつも見られる光景ですが、最後まで歩けた!!という達成感や感動で顔を紅潮させ友達と賑やかに話していられる様子に、準備を進めてきた役員達も胸を熱くさせ涙まで浮かべる者も居て、疲れなど吹っ飛んでしまいます。
歩く事は誰にでもできることですが、高齢者にとってはその歩く事が大変であり、歩ける身体づくりを継続してきたからこそ得られたこの感動や喜びや仲間達との絆は何ものにも代え難い事であり、高齢者にとってはとても大切な事と思います。

●「歩く」ことより「歩ける身体をつくる」こと
こう話すと、私のレッスン指導は、「歩くこと」に重点を置いていると思われがちですが、実際の目的は「歩ける身体をつくる」こと。
そのためのストレッチングや筋力トレーニングが中心ですが、最近は認知症予防運動も取り入れています。
『ヘルシーデザインノート』を毎日つける事。これも脳トレになるのです。
血圧、体重、歩数等の記録を取る事は健康づくりには欠かせませんが、字を書く習慣も大切で、このノートの中には、今週の四文字熟語やキーワードなどがあり、脳を活発に働かせるにとても重宝しています。
生徒さんの中には付ける事を忘れる方もいらっしゃるので 時々見せてもらっています。
研究所の教室の生徒さん方は一度入会されると、重い病気にでもならない限り、教室を辞めるという生徒さんはまずいません。
辞めてしまうと運動する機会も無くなってしまい、自分を駄目にしてしまうという思いと皆さんの絆がより強い結びつきである事でしょうね。
30年以上も通い続けている人もいますし、指導者達も私も教室の皆さんをまるで家族のように親しくさせてもらっています。
そのためには、いろいろと工夫されたレッスンプログラムで基本的な身体づくりすると共に、ウォーキングは1週4~5日自宅周辺を、日曜だけは愛媛県美術館前に集合し皆でいろいろな所へ1時間位歩きます。
その時は、胸に会員証をさげ 帰りに印鑑をおしてあげますが、カードの裏には、万一に備えて顔写真と名前、かかりつけの病院、緊急連絡先などを記載したものを常に携帯してもらいます。
これも7年間一週も休まず続けています。
マスコミも良く取り上げて頂き、先日、NHKのテレビで四国全域に放映された時は、電話が鳴り続けましたが、新聞等にも取り上げて下さるため「ノルディック・ウォーク」の言葉や関心を持つ方も増えてきています。
ウォーキングは年に6回位遠出をします。
日帰りから一泊の小旅行、海外へも出かけますし、全国大会への参加もその一つです。
この他に1年の締めくくりは、ホテルを借り切っての「クリスマスパーティー」を300名位で楽しみます。

●行政とのコラボでメタボ解消を実践
国の助成金事業で西予市(愛媛県)ではメタボリックシンドロームと診断された住民の50代から70代後半の方々50名を集めて、効果測定を行ったことがあります。
期間は3ヶ月間、愛媛大学医学部、自治体、地域医療関係、医療機器関係者と住民の皆さんでPCを使って体重、血圧、歩数等の管理をしながら、私達健康運動指導士が週2回の指導を行いました。
参加された皆さまもやる気があり、とても楽しく続けられました。その結果、全員目標に達しメタボ脱出に成功。
皆さん、大喜びでした。
これは継続しなければと住民の皆さんが立ちあがり「いきいき健康大学」を設立し 現在も続けています。
松山市でも愛媛大学医学部とオムロンとの共同で、様々な効果測定と共に基礎的な体力づくりの講座を行いました。
100名の募集に対し、250名の応募があり大変好評だったので8年間続きました。
松山市では現在、新しく「ノルディック・ウォーク教室」として講座を始めています。
運動による効果は様々に調べてきましたが、全てにおいて良い値が出ました。
いつも良い結果がでるのは 参加者ご自身が実行されたためで私は参加者の雰囲気づくりをしているだけです。
皆さんにはその間に継続しようとする心や支えあう友達をつくって頂く事、指導者は、それにしっかりと答えることが大切だと考えています。

●弘法大師1200年にウォークイベントも
来年は弘法大師生誕1200年ですので、その関連イベントを検討中です。
今年春、第2回ノルディック・ウォーク全国大会として、初めて六ヶ寺を廻るお遍路コース(20km)IVV認定コースを設定しました。
四国は「おもてなし」の国ですから各団体にご提供頂いたジュースやおにぎり・豚汁などを、各お寺の所やその近くでいろいろと用意し役員達から「お疲れ様!」と声をかけられるとホッとされるようで、「美味しいです!御馳走様!」と明るい笑顔で歩いていかれました。
この大会は、のべ300名ほどのボランティアにご協力いただきましたが、なんと70代以上の高齢者の方ばかりだったのです。
でもどなたも、お役に立つ事が嬉しくて、その姿は若々しく活き活きとしていらっしゃいました。
こうした仲間達から元気を頂いて、来年ももっと内容を充実して様々な取り組みをしていきたいと毎日考えている私が、一番幸せなのかも知れません。
皆さんも四国松山のウォーキングを楽しみ 道後のお湯にゆったりとつかりに来られませんか。

<プロフィール>
愛媛大学教育学部卒業・愛媛県立高等学校教諭を経て、松本陽子健康体操研究所設立(1979年)。
えひめ体操フェスティバル3000名大会主催(84年~01年)、松山祭り優勝チームの演出(81年~08年)、日本健康運動指導士会愛媛県支部設立初代支部長(93年~95年)、愛媛県高齢者体操指導者養成セミナー主催(98年~現在に至る)などを歴任、最近は主に高齢者の健康づくりのために活動中。
ノルディック・ウォークを四国に普及すべく、愛媛県ノルディック・ウォーク協会を設立(09年)。